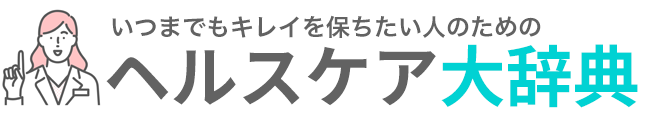40代から体が変わる理由
「最近、疲れが取れにくい」「以前より体調の波が気になる」——そんな変化を感じ始めたら、40代 栄養不足に目を向けるタイミングかもしれません。年齢とともに基礎代謝や筋肉量は緩やかに低下し、食事量も少なくなりがち。すると、中年 必要な栄養素を十分に摂っているつもりでも、実際は足りていないことがあります。とくに筋肉・骨・血液・エネルギー代謝に関わる栄養素は、健康維持の「土台」。ここでは、40代50代で不足しやすい5つの栄養素に絞って、理由と対策をわかりやすく整理します。
不足しがちな栄養素5つ
タンパク質:筋肉と代謝の要
どんな栄養素?
筋肉・臓器・皮膚・髪・ホルモンや酵素など、体の材料になる基本栄養素。加齢に伴う筋量低下をゆるやかにするうえで、日々の十分な摂取が大切と考えられています。
どれくらいが目安?
日本の食事摂取基準では、成人の推定平均必要量は体重1kgあたり0.66g/日が根拠として示されています(一般的に推奨量はこの値よりやや多め)。一方、海外の専門家グループでは高齢期(65歳以上目安)で1.0~1.2g/kg体重/日を目安とする提案があり、運動を行う人はやや多めが望ましいとする立場もあります。食事での分配は1日3食に均等(例:1食20~30g)にすると筋たんぱく合成の観点から合理的とされています。
不足すると?
「疲れやすい」「階段がつらい」「髪や肌のハリ不足を感じる」などの変化につながると考えられています。まずは毎食に“主菜”をのせる意識から始めましょう。
カルシウム:丈夫な骨と歯のために
どんな栄養素?
骨や歯の主要成分。筋肉や神経の働きにも関与します。40代以降は骨量が減りやすく、意識して確保したい栄養素の一つです。
どれくらいが目安?
食事摂取基準(2025年版)の推奨量は、例として男性30~49歳750mg/日、50~64歳750mg/日、女性30~64歳650mg/日などが示されています。
不足すると?
骨密度の低下につながるおそれがあるため、毎日の食事での積み上げが重要です。
ビタミンD:カルシウムの相棒
どんな栄養素?
カルシウムの吸収を助け、骨の健康維持に役立つ脂溶性ビタミン。食事から摂るほか、日光(紫外線)を浴びることで皮膚でもつくられます。
どれくらいが目安?
日本の食事摂取基準(2025年版)では、成人の目安量がおおむね9.0μg/日前後、過剰摂取を避けるための耐容上限量は100μg/日と設定されています。
不足すると?
骨の健康だけでなく、加齢に伴う体力低下にも関わるとの報告があり、カルシウムと一緒に確保することが勧められています(相互作用が示唆)。
ビタミンB群:エネルギー代謝の要(B1・B6・B12など)
どんな栄養素?
糖質・脂質・タンパク質をエネルギーに変える“作業員”のような存在。とくにビタミンB1は糖質代謝に、B6はアミノ酸代謝に、B12は赤血球の成熟に関わるとされています。
どれくらいが目安?(B1の例)
2025年版のビタミンB1推奨量は、男性30~49歳1.2mg/日、50~64歳1.1mg/日、女性30~49歳0.9mg/日、50~64歳0.8mg/日など。糖質の摂取が多い人や活動量が多い人は、より必要量が増えやすい点にも注意が必要で
鉄分:酸素を運ぶミネラル
どんな栄養素?
赤血球のヘモグロビン成分。40代以降も、とくに女性は月経の有無で必要量が変わります。
どれくらいが目安?
食事摂取基準(2025年版)の推奨量は、例として男性18~64歳7.0~7.5mg/日、女性18~64歳は月経ありで10.0~10.5mg/日、月経なしで6.0mg/日など。サプリの過剰摂取は鉄の蓄積につながる可能性があるため、自己判断での高用量は避け、医療者に相談するのが安心です。
各栄養素を含む食材リスト
数字は目安量。日々の献立づくりの参考にしてください。
タンパク質
-
卵:1個(50g)で約6gのたんぱく質。朝食に1個足すだけでベースアップ。
-
納豆:1パック(50g)で約8g。発酵食品として腸内環境にも役立つとされます。
-
豆腐:絹ごし100gで約5.3g(150gで7~8g)。みそ汁や冷ややっこに。
カルシウム
-
牛乳:コップ1杯200mLで約220mg。無理なく毎日続けやすい。
-
小魚・青菜・大豆製品:骨ごと食べられる小魚、青菜、豆製品もこまめに。
ビタミンD
-
さけ(紅鮭):可食部100gで約32μg(魚種・部位で差)。和食の主菜に取り入れやすい。
-
きのこ類:食材中のビタミンD(D₂)源。汁物や炒め物で。
ビタミンB群(とくにB1)
-
豚肉・魚・豆類・玄米:主食を“白→雑穀・玄米”に一部置き換えるのも一手。
鉄分
-
赤身の肉・魚(ヘム鉄)、大豆・ほうれん草など(非ヘム鉄):ビタミンCを合わせると吸収がよくなるとされます(例:肉+野菜、豆+柑橘)。